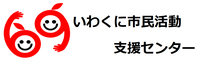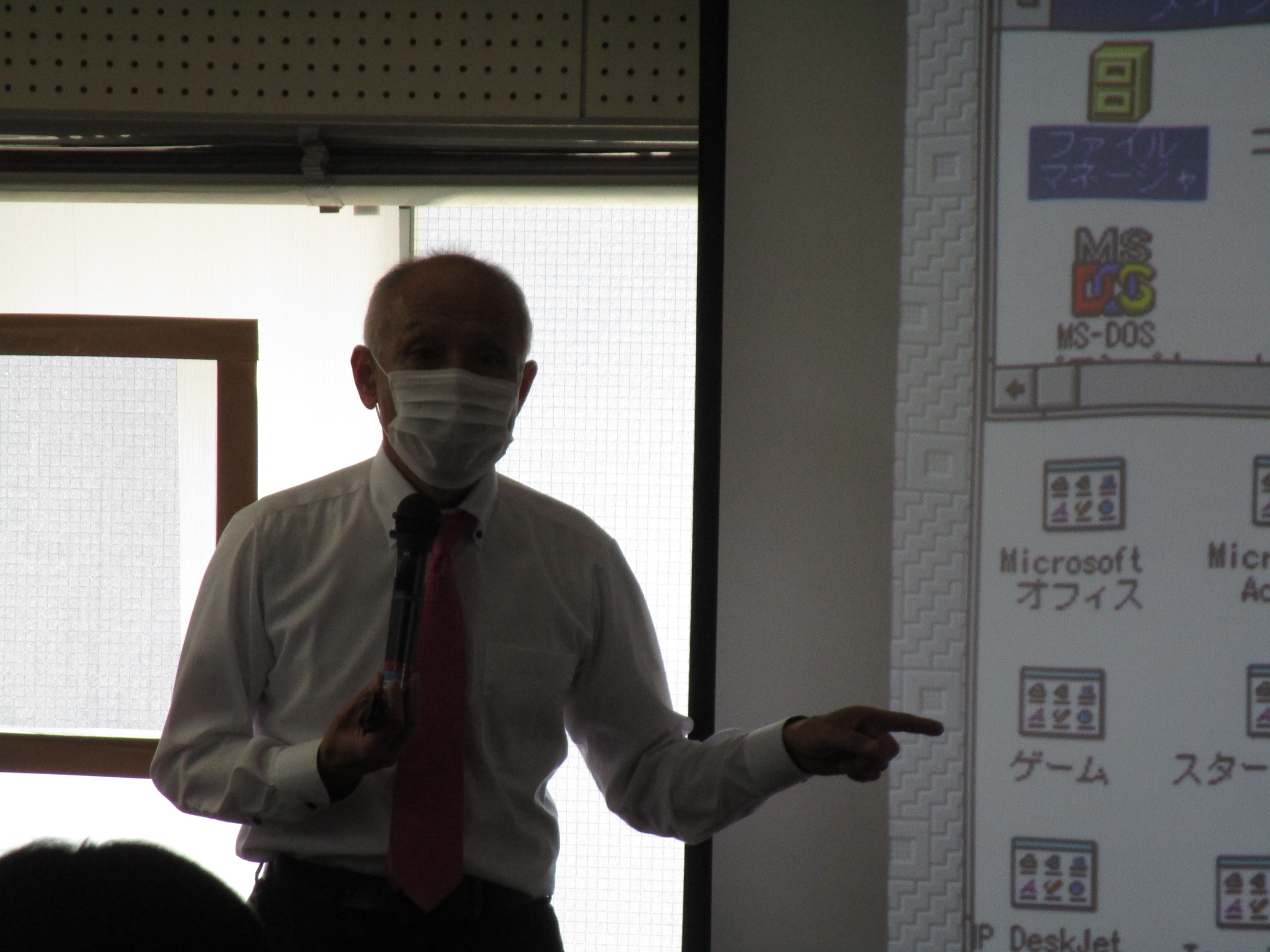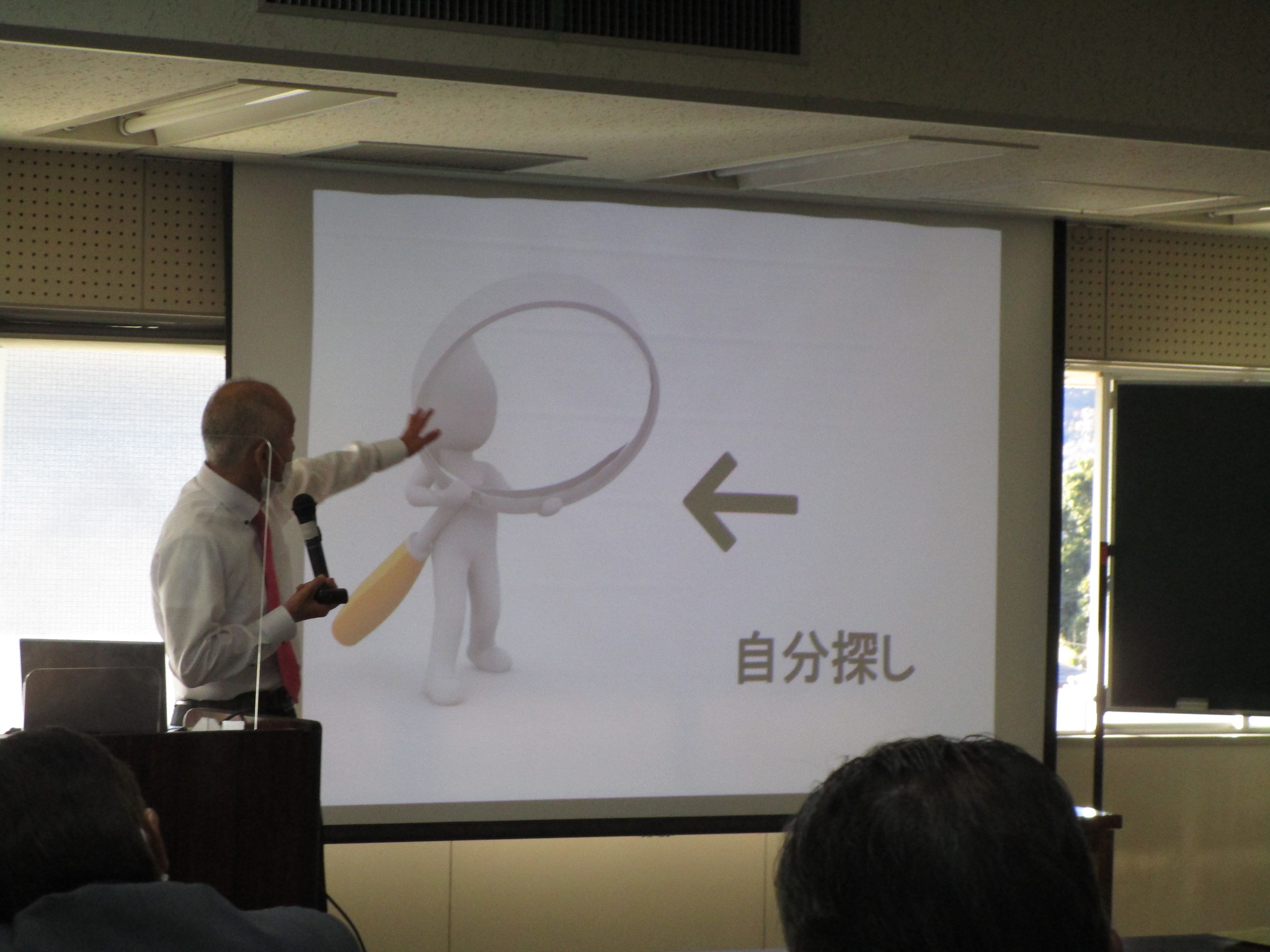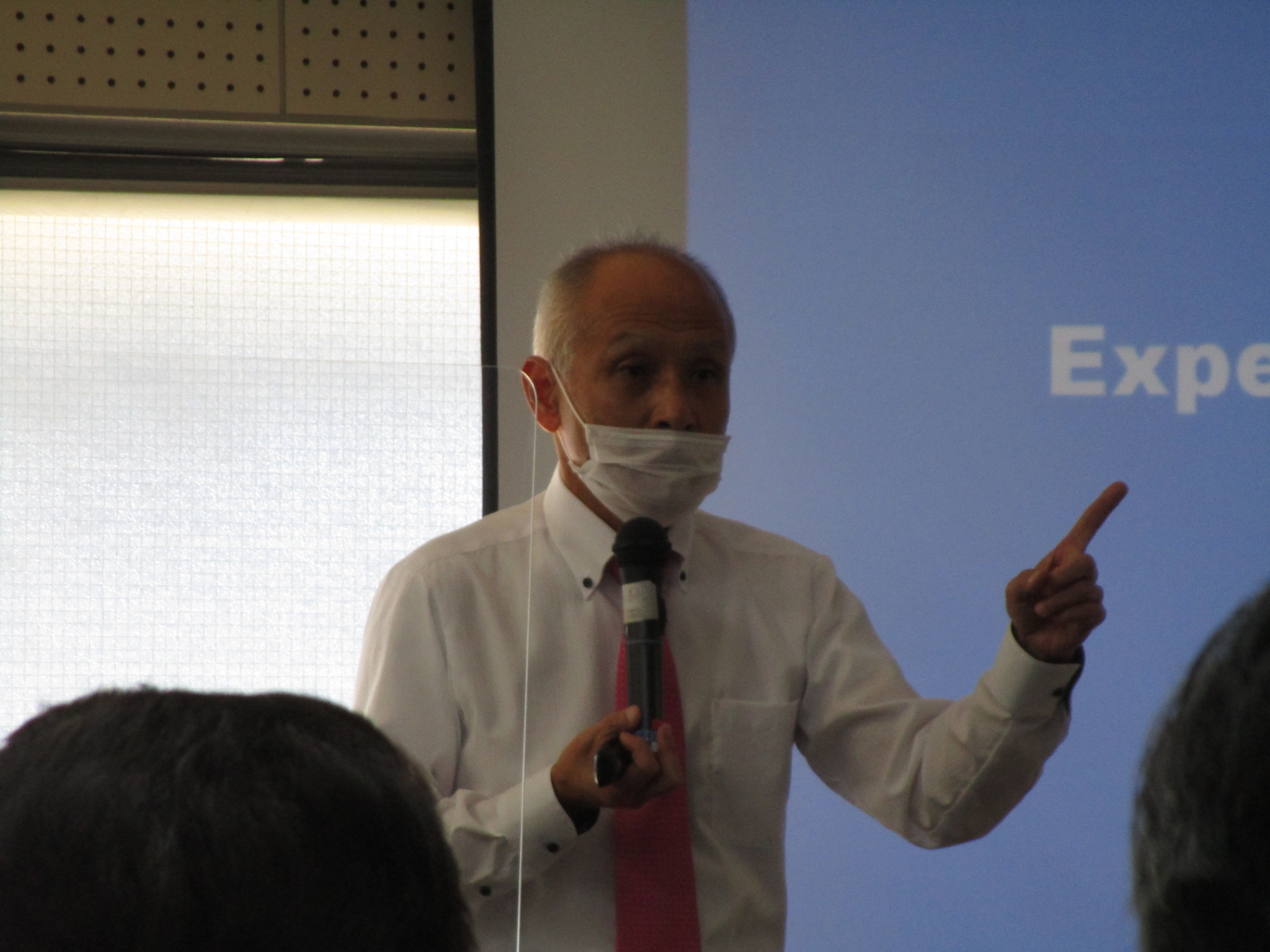日 時:2020年11月21日(土)13:30~15:30
場 所:岩国市中央公民館 第4講座室
講 師:黒川康生氏(元県立高校教諭)
参加者:13名
●講師紹介
昨年、県立高校教諭を定年退職。在任中も県庁職員や防府市観光協会等に関わり、防府市「幸せます」プロジェクトの普及や「世界お笑い協会」副会長としてまちづくりに携わる。
現在は、デザイン事務所顧問、防府市市民活動支援センターの職員等の傍ら、地元大手スーパーの人材育成指導役としても活動している。
●講座
〇パワーポイントのはじめ
・ハードウェア(コンピュータ)=土地
ソフトウェア=家
Windows3.1=家の基礎
・1995年に初のソフトウェア日本版リリース=パワーポイント
スライドプレゼンソフトのリリース時より、日本での利活用始まる
→情報デザイン(情報を扱い、問題を解決する)→情報を整理しわかりやすく伝える
〇プレゼンテーションはドラマである
プレゼンの主役は聴衆(オーディエンス)である
〇ドラマにはストーリーがある
ストーリーの展開が大事
聴衆のための情報は、視覚ではなく耳で伝える(視覚は補足)
〇人間は同時に複数の情報を受信できない
〇うまくまとめられた文章と、口頭による優れたプレゼンテーションとは全く別物である
〇スライドは口頭によるプレゼンの視覚的サポートである(情報は聴覚から入る)
〇単純であることは究極の洗練である
〇人は感情で行動する(商品の写真と共に事例を紹介)
【防府市「幸せます」ブランドを高校生と商品開発した事例】
・商品化は簡単だが”売る”ことが一番難しい→消費者の心に響かないと売れない
・”売ることを考え、作る”→感情のトリガーを引くこと→人は感情によって行動する(モノを買う)
・人はモノそのものではなく「世界観(意義・価値・雰囲気)」を見ている(空間と時間に感情が動く)
・経験経済→感動と興奮は消費に結びつくということ
〇コミュニケーションは、背景の共有から
【地方創生/消滅可能性都市の例】
・定住人口や交流人口など人口を増やすことばかり考えるとまちはつぶれる
現代の子供達が故郷に残るためには思い出を残すことが大事
・背景がずれたら会話にならない。主役がオーディエンスということ。
【自分探しの例】
・相互協調的自己感と相互独立的自己感
・他社や周囲との関係の中で自己の解決したい問題探しが見つかる
・仕事とは、出来事の連続、他者との関わり合い、自分を知ること
・仕事力とは、自分・他者・出来事という対象と向き合う力
→物事の本質を理解する力(背景・感情・意味・価値)自分で問題を理解する力(疑問・不調・失敗・困難)
〇プレゼンテーションのまとめ
主役は聴衆(オーディエンス)
情報は口頭によるプレゼンテーション(資料作りではない)
スライドは簡潔に(メッセージ)
適切なイラスト、インパクトあるメッセージ、単語で印象付ける
話の「背景」を共有する
良いプレゼンテーションを見て学ぶこと(この講座が見本)
●アンケート結果
1.この講座はいかがでしたか。
大変参考になった 8
参考になった 3
参考にならなかった 0
2.今までのプレゼンテーションで伝えたいことは正しく伝わっていますか。
主役は自分だとよくわかった
わからないが、インパクトには欠けている
伝わっていない、いなかったと思う
全く伝わっていない
3.講座の中でどんな内容が印象に残りましたか。
世界観の見分けと背景の共有
①単純であること②背景の共有③ドラマにはストーリーがある
プレゼンとは、オーディエンスが主役
オーディエンスを考えながら行動していきたい
シンプルisベスト
情報の伝え方の例としてされた先生の話
プレゼンの見せ方の講座だったが、先生の学校での授業や、会社での話が聞けて面白かった
4.この講座を学ばれて、今後の活動にどのように役立てられますか。
自身でプレゼンをしていきたい
仕事で活かしていきたい
まずはプリントで復習
絵を描いているので、何を伝えるか、その伝えたいことの組み立て方に役立つと思った
5.「共感」を得るため、「伝え方」は何が一番大事だと思いますか。
主役の見極め
説得力
言葉が大切である
背景の共有
相手の立場に立つこと
6.この講座をどうやってお知りになりましたか。
ホームページ・市報 0
チラシ 4
知人 2
いわくに市民活動支援センター 3
その他(中国新聞) 2